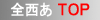
| → |
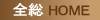
| → | 用語解説の索引 | → | このページ |
|---|
| 五全総用語解説をチェック! 第1部編 国土計画の基本的考え方 |
|---|
| 索引に戻る | 第1部 | 第2部第1章 | 第2部第2章 | 第2部第3章 | 第2部第4章 | 第2部第5章 |
|---|
| 索引に戻る | 第1部 | 第2部第1章 | 第2部第2章 | 第2部第3章 | 第2部第4章 | 第2部第5章 |
|---|
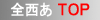
| → |
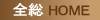
| → | 用語解説の索引 | → | このページ |
|---|
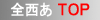
| → |
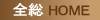
| → | 用語解説の索引 | → | このページ |
|---|
| 五全総用語解説をチェック! 第1部編 国土計画の基本的考え方 |
|---|
| 索引に戻る | 第1部 | 第2部第1章 | 第2部第2章 | 第2部第3章 | 第2部第4章 | 第2部第5章 |
|---|
| 索引に戻る | 第1部 | 第2部第1章 | 第2部第2章 | 第2部第3章 | 第2部第4章 | 第2部第5章 |
|---|
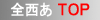
| → |
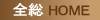
| → | 用語解説の索引 | → | このページ |
|---|