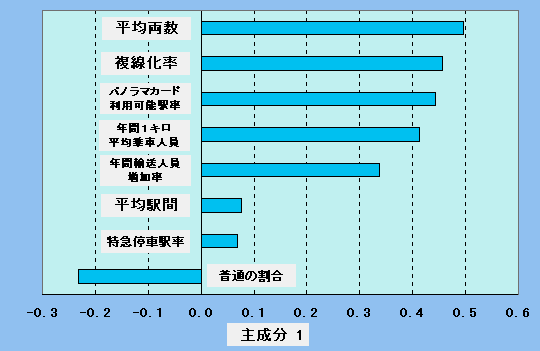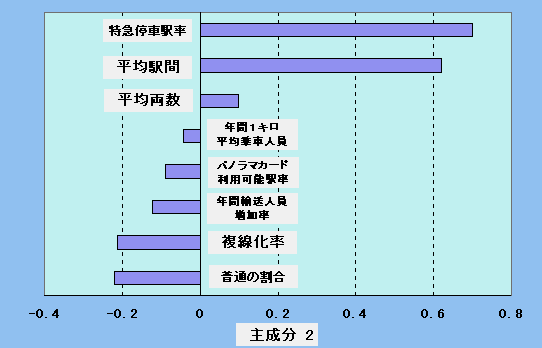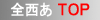
| → |

| → |
| → | このページ |
|---|
西尾線の特徴
2つの指標の名称の決定
|
主成分分析の計算をして各路線の性質を示す2つの新しい指標(主成分)を求めることができました。
しかし、その指標が何を表しているかを理解しないと路線ごとの性質なんてわかりません。 このページでは、2つの指標の意味合いを考察します。 これが、一番難しいプロセスです。反論も多いかもしれません。 とりあえず、ご覧ください。 |
| 前のページに戻る |
|---|
|
まず、各路線の性質を示す指標値はこのような式で表されます。
(西尾線の性質を示す指標値①)=a×(西尾線の平均駅間)+b×(西尾線の複線化率)+・・・
そして、上式のa,b,・・・を前段階で求めました。2つめの指標(②)も同じく係数を求めました。
つまり、各路線の指標①(第1主成分)の値は 0.08×(その路線の平均駅間)+0.46×(その路線の複線化率)+・・・・ となります。ただし、平均駅間や複線化率はそのものの値ではなく、 標準化した値(平均0,分散1に整理した値)を用いています。 では、新しく出来た指標(主成分)の意味付けをします! さきほどの表を大きい順に並び替えてグラフ化しました。
【第1主成分】
つまり指標①(第1主成分)は、「平均両数が長く」「複線区間が多く」
「パノラマカードが使える駅が多く」「乗車人員が多く」「普通の割合が低い」
路線ほど大きい値となることがわかります。
指標②(第2主成分)は、「普通列車の割合が多く」「複線で」「平均駅間が短く」「特急停車駅が少ない、または"ない"」
路線ほど大きい値となることがわかります。 |
| 前のページに戻る |
|---|
| これが、西尾線。のHOME |
|---|