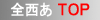
| → |
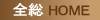
| → | このページ |
|---|
|
平成10年3月31日、5番目の全総である、
「21世紀の国土のグランドデザイン -地域の自立の促進と美しい国土の創造-」
(以後、五全総と称します。)が閣議決定されました。 五全総は今までの全総と一線を画しています。 いままでと違う全く新しい全総を策定しようということから、名称も 「第五次全国総合開発計画」ではなく、このような名称になりました。 このページでは五全総の特徴、今までの全総との違い等、まとめたいと思います。
「21世紀の国土のグランドデザイン」については五全総の第1部・第1章において述べられています。 そこでは、五全総の施行期間、つまり今後21世紀初頭にかけては、 国土とそれを構成する地域とをめぐる諸状況は、戦後のそれとは 大きく異なるものになると指摘し、具体的には次の4項目を挙げています。
①国民意識の大転換:量より質、所得よりゆとり、
また自由な選択や自己責任、自然への再認識、男女平等への変換 そして、これらに対応した社会を創造することが 「21世紀の国土のグランドデザイン」の構想であるとしています。
「21世紀の国土のグランドデザイン」の構想を実現させるために、
次のような基本目標が提示されました。
【ステップ1】
【ステップ2】
【ステップ3】
【ステップ4】 つまり、これまでの全総で解決しようとしてきた「地域格差」は、 この国土構造によるものと考え、根本的にそれを転換する ことにより、諸問題解決を目指そうとしたといえます。 そして国土構造の変化は、社会状況が変化したときに起こっていることから、 先に述べた通りの将来展望のもとでは国土構造転換を するのに可能な時期としています。 それを踏まえて五全総では、「多軸型国土構造形成の基礎づくり」の推進を提示しています。 つまり、様々な共通性を持った地域の連なりが圏域としての輪郭を次第に明瞭にし、 その圏域(国土軸)が複数存在することにより、 相互に連携して国土を形成していく国土構造を目指しているわけです。 具体的には以下の4軸を構想しています。
①北東国土軸:中央高地から関東北部を経て、東北の太平洋側、北海道に至る地域。 太平洋ベルト地帯は明治以降100年を超す時間が費やされて形成されたことから、これら 4軸も長期的な視野に立って取り組むとしています。
全総を策定する際、四全総までは、次のようなフローとなっていました。
①現状、基本課題の把握 五全総に置きかえると、①は「地球時代」「人口減少,高齢化時代」「高度情報化時代」等、 ②は「多軸型国土構造形成の基礎づくり」であり、 上のフローでいくと次は何らかの開発方式をとって、 「多軸型国土構造形成の基礎づくり」という目標を達成させる訳ですが、 五全総では、開発方式を提示していません。では、それに変わって何を提示しているかというと、 「参加と連携」です。 ごく簡単にいうと、それは「地方や民間企業に委ねる方式」といえます。 つまり、四全総までの開発方式では、例えば一全総の拠点開発方式のように全国一律で 同じ方法をとって開発を進める方式でした。しかし、五全総では各地域の個性や多様化を尊重し、 地方団体等への「呼びかけ型」の計画方式に変化しています。
しかし、「五全総の開発方式は"多軸型国土構造形成の基礎づくり"である」と感じてしまうのは僕だけでしょうか? |
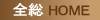
|
|---|